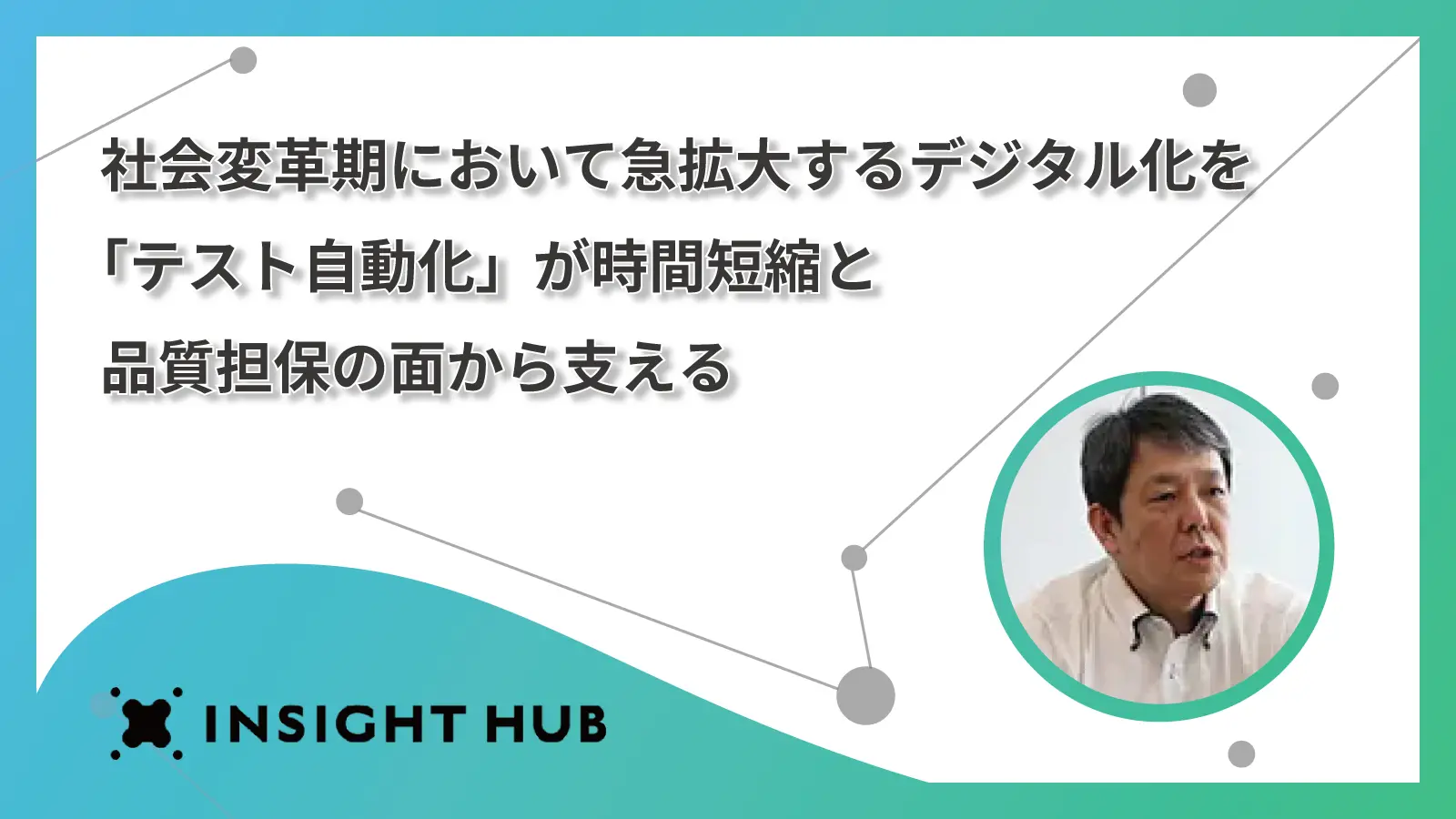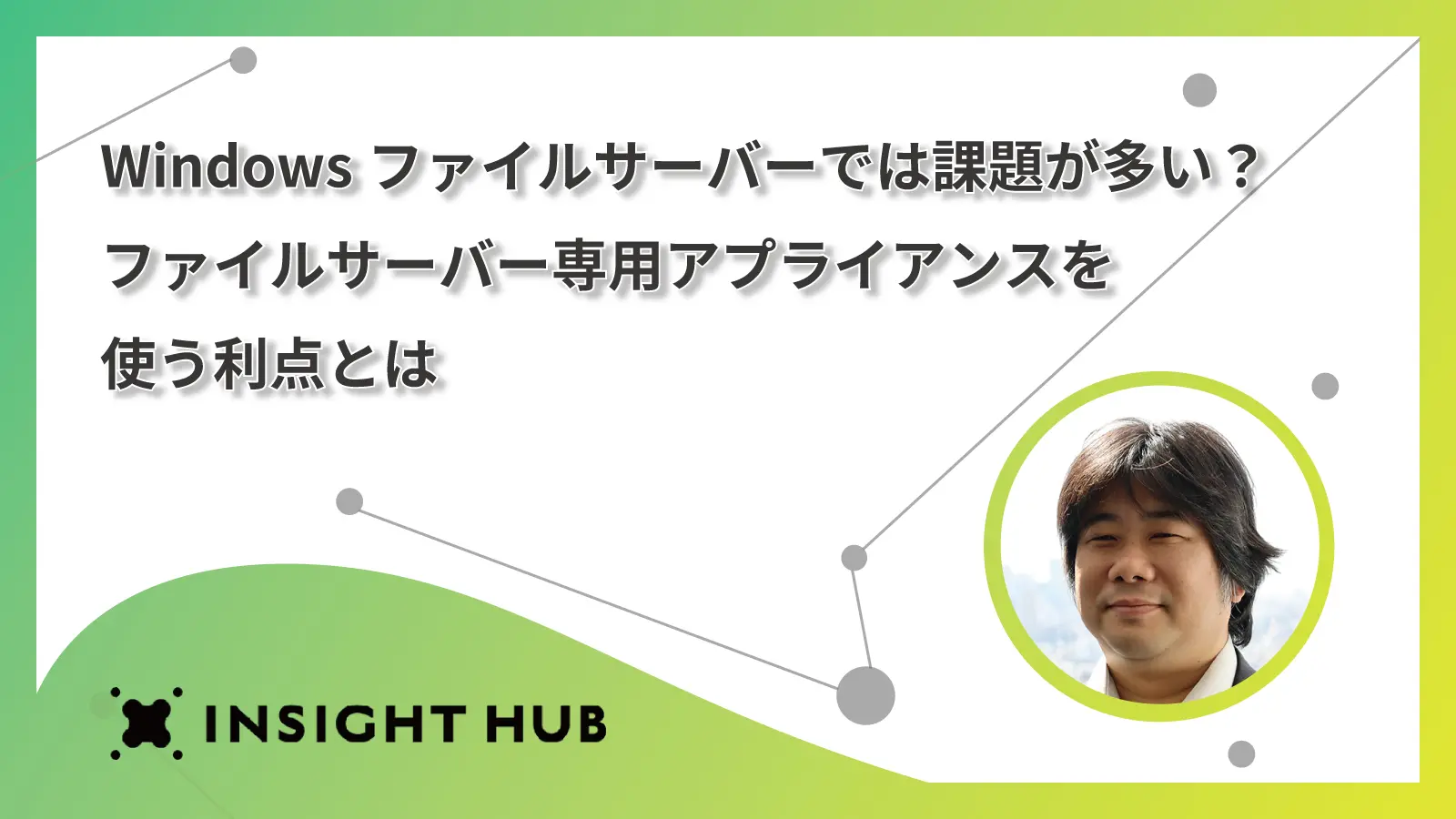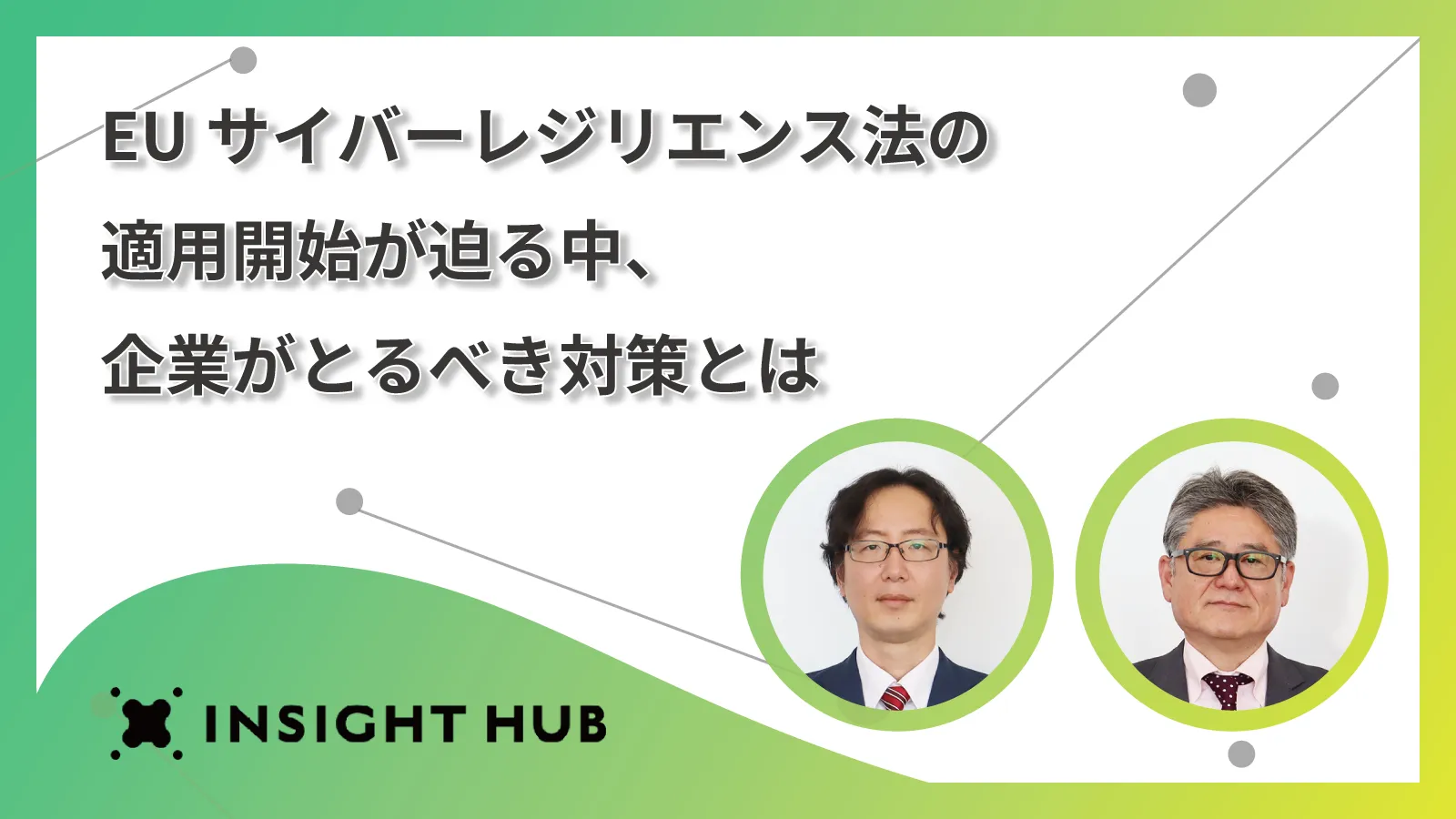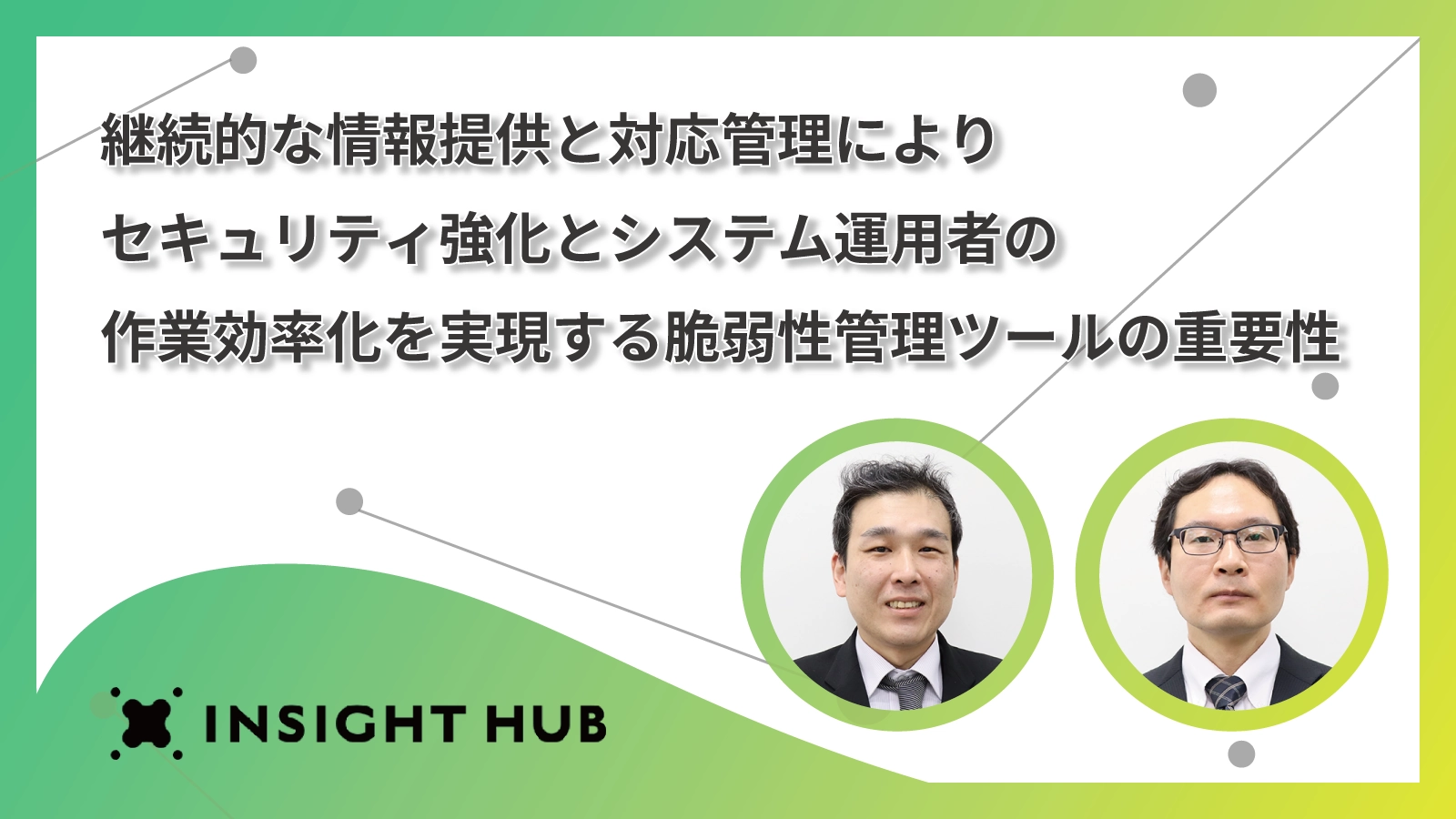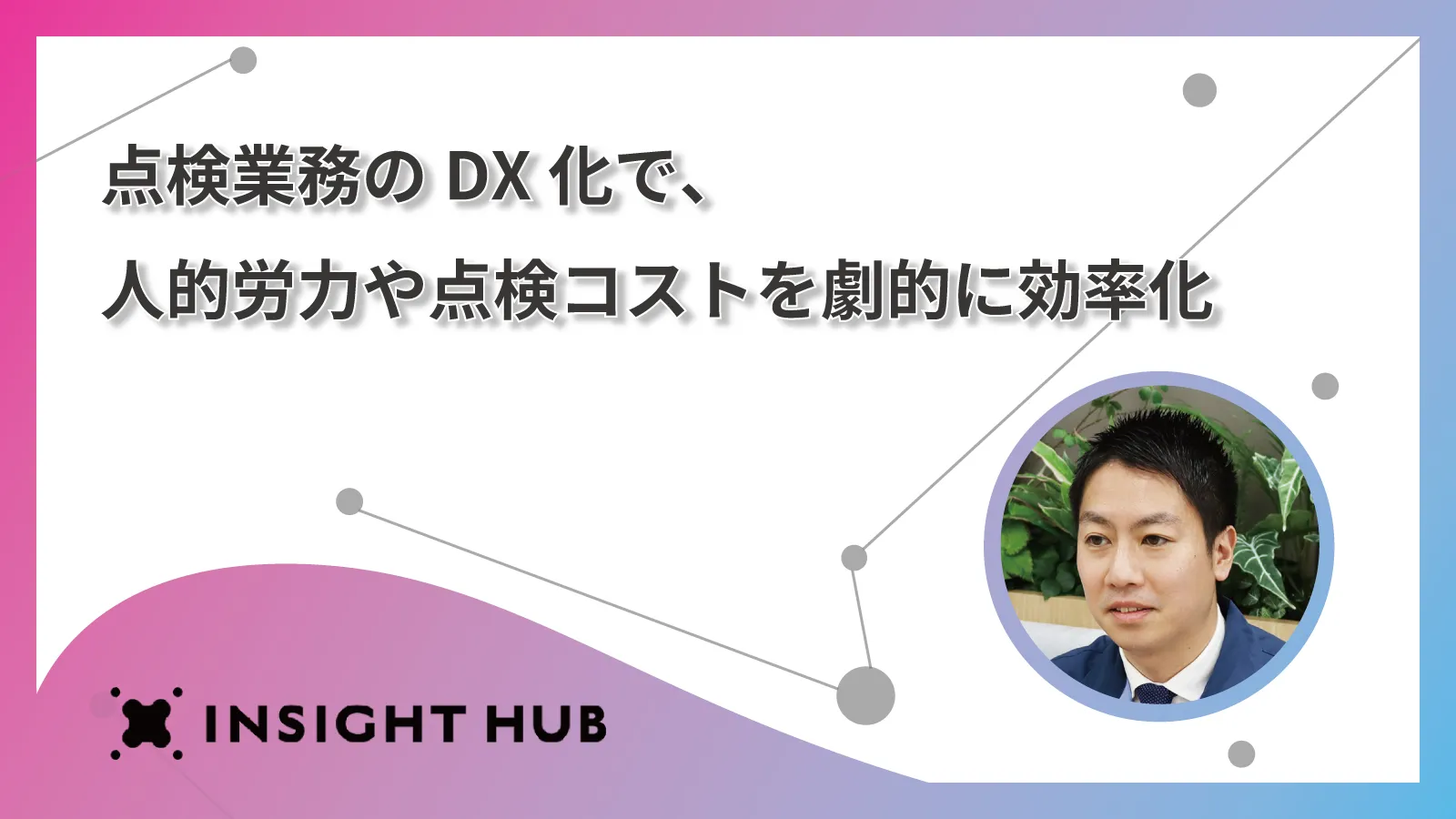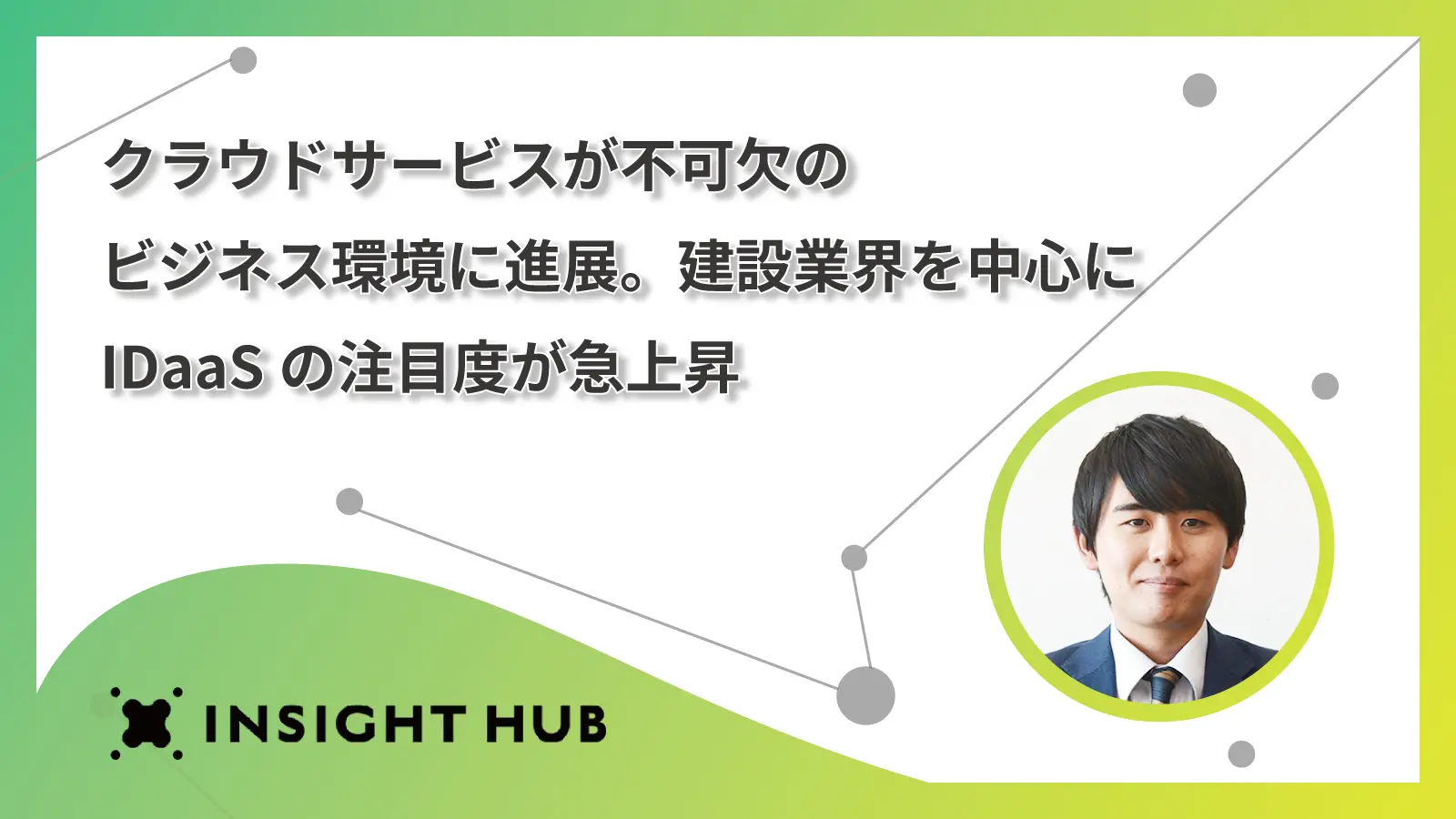製造業の「デジタル化」は避けられない課題
長引くコロナ禍の中で、様々な業種、業界が大きな変化を求められています。それは、製造業も例外ではありません。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、部材の調達や物流などのサプライチェーンに支障を来し、供給面でも甚大な影響を与えました。製造現場は、ニューノーマル時代に合った業務の進め方を確立させる必要があるでしょう。
経済産業省などが公表している「2021年版ものづくり白書」では、製造業がニューノーマル時代を生き残るために、3つのキーワードとその具体的な強化ポイントを掲げています。しなやかな回復力を意味する「レジリエンス」は、サプライチェーンの強靭化、環境対策の「グリーン」は、二酸化排出量を実質ゼロにするカーボンニュートラルへの対応、「デジタル」はDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組み深化、といった具合です。
例えば、デジタル化の促進、DXの取り組みによって、設計開発や生産、顧客データの連携やAI(人工知能)による予測・予知、3D設計や3Dプリンターの活用による製品開発のスピードアップ、変種・変量や生産プロセスへの柔軟な対応などが、大きく進展すると見込まれています。
また、製造現場では金型の作成など、職人の方々が長年蓄積してきた技術の継承や、若手技術者の育成も深刻な課題となっています。これまで属人的になりがちだったものづくりの技術習得においても、デジタル化が進むことで、平準化できるようになるでしょう。
3Dプリンターは“イノベーションの壁”を打ち破る
こうした状況において、3Dプリンターはものづくりのプロセスを革新すると期待されています。というのも、製造業が直面する“イノベーションの壁”を打ち破る可能性があるからです。その1つが、プロダクトイノベーションの壁。従来の金型や切削加工でつくる部品の形状には制約があり、複雑な形状は困難です。
一方、樹脂や金属などの材料を付加しながら製造する3Dプリンターに代表されるAdditive Manufacturing(付加製造)は、形状におけるハードルを乗り越え、切削加工では困難な造形にも対応し、プロダクトイノベーションが実現できます。
金型は製作に時間がかかり、新製品投入までのリードタイムが長くなりがちといった課題もあります。Additive Manufacturingであれば、よりスピーディーに設計から生産へと進められ、製造現場に求められるプロセスイノベーションを起こすことが可能です。このほか、部品などの在庫を持つ必要がなく、オンデマンドでの造形が可能、切削加工に比べて作業者の負担が少ない、といった利点もあります。
この造形技法を活かした3Dプリンターには、製造現場のDXを後押しする様々な活用法が考えられます。例えば、試作を内製化することで、外注時の納品を待つことなく開発期間が短縮できるでしょう。加えて、設計やデザインの段階から実際のモデルを造形すれば、3D設計データの画面では分からなかった問題点を見つけるなど、事前検証を繰り返すことで、金型の作り直しなど無駄な工程やコスト削減が見込めます。
3Dプリンターは製造現場に大きな変革をもたらすとはいえ、万能ではありません。金属粉末と熱可塑性のバインダー(結合樹脂剤)を混合した材料を加熱して吐出、積層するBMD(Bound Metal Deposition)方式を採用する金属3Dプリンターの場合、高温で金属粉末を溶融結合させて焼結体をつくるファーネス(焼却炉)の工程で、造形物が壊れることもあるからです。日本の製造現場では、従来の金型、切削加工と同等の高い強度や精度、品質が求められます。そのため、材料に応じた焼結の温度や時間などの研究、検証が欠かせません。
30年近くにわたる3Dプリンター支援の実績を生かす
手軽な金属3Dプリンター「Studio システム 2」
丸紅情報システムズでは、2018年より米国Desktop Metal社の金属3Dプリンター「Studio システム+」を取り扱い、小型・少量生産に適した金属3Dプリンターとして評価しています。2021年2月には、その後継機となる「Studio システム 2」の取り扱いを開始しました。
Studio システム 2は、バインダーの脱脂と金属粉末の溶融結合をファーネスの1ステップで行いますが、従来のデバインダー(脱脂専用装置)が不要です。造形と脱脂・焼結の2ステップで造形が完結できるため、従来の脱脂における有機溶剤使用が導入障壁になっていた企業や大学、研究機関などでも採用しやすくなりました。Studio システムは専用ソフトウェア「Fabricate」によって造形、脱脂・燃焼の一括管理、制御を行い、手軽に金属3Dプリントを実現できる点が大きな特長です。
丸紅情報システムズは、1992年以来、30年に亘り企業や研究機関などへの3Dプリンター導入と活用を支援してきました。3Dプリンターの販売・保守サポートで培ったノウハウ、技術力を生かし、ものづくりのプロセス、プロダクトで3Dプリンターをどのように使いこなすかといった相談や、ベンチマークの実施、サブスクリプションやタイムシェアリングによるレンタルサービスもご用意しています。
さらに、お客様の3Dデータを元に実際に形にするオンデマンド造形サービス、形状や材料などのコンサルティングサービスなどのソリューションも提供します。お客様の要望をヒアリングして、試しに造形するといったことも可能です。Studio システムで出力した造形物の強度を確かめたい場合、内部の状態を測定する産業用CT事業もグループ会社で実現できます。
このように丸紅情報システムズは、ものづくり現場における金属3Dプリンターの活用を通じ、引き続き製造業のDXを推し進め、ものづくりが直面する課題解決やイノベーションの創出を強力にサポートしていきます。